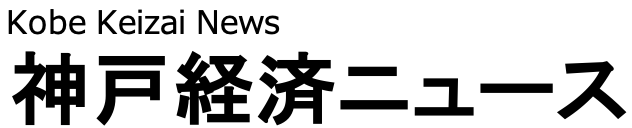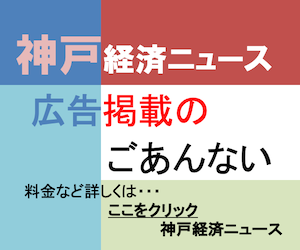復興基金解散で「感謝のつどい」 井戸知事「現場に任せ多くのきめ細かい事業」
- 2021/07/27
- 03:03
7月末で解散する公益財団法人の阪神・淡路大震災復興基金は26日、同基金としての最後の事業として「感謝のつどい」を兵庫県公館で開催した。基金の理事長を務め、同じ7月末で退任する兵庫県の井戸敏三知事はあいさつし、「国が考えたメニューでは被災地はついていけないということで、基金の使い道が現場に任せられるようになってから、多くのきめの細かい事業ができるようになった」と振り返った(写真)。「被災者や現場の声をどう反映するか、というのに応えることができた仕組みではなかったか」と、意義を強調した。
生活再建のための資金を被災者に提供し、当時は制定前だった被災者生活再建支援制度の代わりになるなど大規模な事業を手がける一方で、震災前や仮設住宅のときといった過去に属したコミュニティ(ご近所の人間関係)を訪ねて旧交を温めるための交通費の補助なども実施。「1回数百円単位の事業までできたのも、きめの細かい対策ができたことを示している」(井戸知事)と話していた。神戸市の久元喜造市長も「市の事業だけでは行き届かなかった部分を、基金が補った」と評価した。
基調講演した室崎益輝・兵庫県立大教授は「ガスや電気を復旧させるインフラ復興から、生活そのものを復興する生活復興や人間復興に変質するのに、復興基金は不可欠な存在だった」と指摘した。利子補給などの金融面に加え、教訓継承の活動、心のケアセンターや高齢者自立支援ひろばといった新しい公的施策の創造など、阪神淡路大震災をきっかけに新たな施策の多くは復興基金が支えになったという。そうした対応ができたのは震災発生後3カ月も経ずに立ち上がった基金の迅速さと、市民の自発性を引き出そうとした理念があったと指摘した。
室崎氏の講演に続く座談会では、コミュニティ・サポートセンター神戸の中村順子理事長が、復興基金の支援をきっかけに始まったボランティア活動が現在でも継続していることなどを紹介。神戸まちづくり研究所の野崎隆一理事長は「地元が主体性を持って復興をめざそうとしたのが阪神淡路大震災の特徴だったが、基金がなければ市民は空回りしていたのでは」と述べ、基金によって住民らの議論やアイデアに現実味が出たのが復興にも寄与したとの見方を示していた。
▽関連記事
- 関連記事
-
- 神戸市の中学モデル標準服、ワールドの「C案」軸にデザインへ 人気投票トップ (2021/07/27)
- 神戸市長選、服部修氏が立候補表明 「兵庫知事選の後に多くのはげまし」 (2021/07/27)
- 復興基金解散で「感謝のつどい」 井戸知事「現場に任せ多くのきめ細かい事業」 (2021/07/27)
- 兵庫県、国の来年度予算に「UNOPS支援」「関西版フラウンホーファー」など要望 (2021/07/27)
- 井戸兵庫知事、コロナ対策「今週中に8月以降の案を示す」「いまの対策継続」 (2021/07/26)
広告