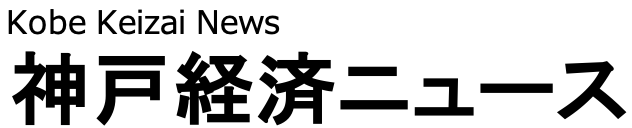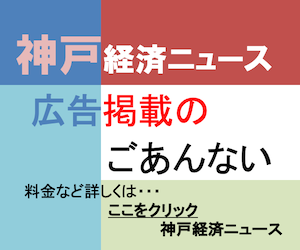関西が結束できる「共通の利益」とは何か? 震災記念21世紀研がシンポ
- 2022/09/28
- 02:56
【神戸経済ニュース】兵庫県の外郭団体である社会科学系の研究機関「ひょうご震災記念21世紀研究機構」(神戸市中央区)は27日、シンポジウム「広域経済圏活性化による経済成長戦略」を神戸市内で開いた。2021年までの4年間に継続的な研究会の開催を通じてまとめた同名の報告書の発表会を兼ね、大阪市で国際博覧会(大阪・関西万博)を開く2025年や、SDGs(国連の持続的な開発目標)がゴールと定める2030年に向けた経済や社会のあり方について議論。大阪を中心とした経済圏の可能性を発揮するためには「関西圏での広域の結束」が必要だと強調した。
基調講演は関西学院大の上村敏之教授が担当。報告書のうち第3部に相当する政策提言「関西は広域で結束せよ」を中心に話した。関西経済からイノベーション(革新、新機軸)が生まれにくい背景には、企業が新陳代謝する市場の健全性が乏しいことや、自治体間の連携不足による産業振興策の不一致、硬直的な労働市場などがあると指摘。府県境などを超えた自治体や企業の多様な連携で、克服する必要があると主張した。
パネル討論(写真)では、同志社大の新川達郎名誉教授が「危機に陥っている関西をなんとかしよう、そこから共通の利益を作り出す社会や経済の構造」が必要だと語った。これにJR西日本(9021)の多田真規子・地域まちづくり本部地域共生部長は、関西広域連合に対応するDMO(観光地経営組織)の関西観光本部が訪日外国人観光客向けに「山陰海岸」「丹波」「淡路島〜徳島」といった府県をまたぐ広域観光ルートを8つ設定していると応じた。
加えて竹中工務店の水方秀也・開発計画本部長は、テレワークの普及などを背景に「大都市の都心で働き、郊外は寝る場所という状態はだいぶ変わるだろう」と指摘。どこにどういった都市機能を配置するかは、より広い視点が必要になるとの見通しを示した。一方で、京都、大阪、神戸と独特の個性を持った都市が連なる関西圏にあっては「成長だけで結束するのは難しく、成長の果実をどう分け合うのかも話す必要がありそう」(関学大の上村氏)との指摘もあった。
このほかパネル討論には大阪大の沢木昌典教授も参加。コーディネーターは、一連の研究会で座長を務めた兵庫県立大の加藤恵正教授が担当した。シンポジウム開催のテーマになった報告書は、ひょうご震災記念21世紀研究機構のホームページに掲載した。
▽関連記事
- 関連記事
-
- 神戸市「アーバンイノベーション」4課題の採用会社が決まる 2課題は共同運営 (2022/09/28)
- 県立兵庫津ミュージアム、11月24日に全面開業 記念行事「踊り念仏」でライブ (2022/09/28)
- 関西が結束できる「共通の利益」とは何か? 震災記念21世紀研がシンポ (2022/09/28)
- 斎藤兵庫知事、県庁再整備「グランドデザインと現庁舎対策を切り分け」 本会議 (2022/09/26)
- 巨大ガチャで10・11月の小売店振興「そろえて神戸」を事前PR 神戸市 (2022/09/23)
広告
chevron_left
3年ぶり「神戸ジャズストリート」にDEPAPEPEが登場 CFで開催資金 home
シスメックス、尿検査の高性能機種を小型化 中小の医療機関など向け
chevron_right